前回の記事では、キャリアを飛躍させる「戦略的雑読」の魅力についてお話ししました。
▼前回の記事はこちらから
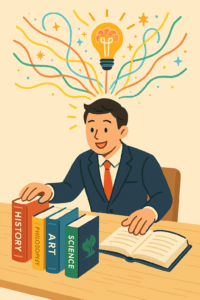
今回はその続編として、「雑読が大事なのはわかったけど、具体的にどう計画すればいいの?」という疑問にお答えします。
戦略的雑読の3つのステップ
「よし、戦略的雑読をやってみよう!」
そう思って本屋さんに立ったはいいものの、
「…で、結局どの本を読めばいいんだろう?」 「『戦略』って聞くと、なんだか難しそう…」
と、無限に広がる本の海の前で、途方に暮れていませんか?
ご安心ください。「戦略」といっても、ガチガチの目標達成計画を作る必要は全くありません。
雑読の戦略とは、いわば自分だけの「知の冒険マップ」を作ること。どこに宝が眠っているかわからないワクワク感を大切にしながら、遭難しないための「ゆるやかなコンパス」を持つイメージです。
今日は、誰でも簡単に実践できる「冒険マップ」の作り方を、3つのステップでご紹介します!
【ステップ1】現在地を知る:自分の「知の偏り」を正直に見てみよう
どんな冒険も、まずは現在地の確認から。あなたが今、どんな知識の場所に立っているのかを把握してみましょう。
やり方は簡単です。
《かんたんワーク》あなたの「本棚」を分析!
- 最近読んだ本10冊を、紙やスマホのメモに書き出してみてください。
- 自宅の本棚や、Kindleなどの電子書籍ライブラリをざっと眺めてみましょう。
- どんなジャンルの本が多いですか? カテゴリーに分けてみましょう。
- 例: ビジネス書(マーケティング、自己啓発)、専門分野の技術書、小説(ミステリー)、マンガ…など
どうでしょう? おそらく、多くの方が特定のジャンルに偏っていることに気づくはずです。
「うわ、仕事関係のビジネス書ばっかりだ…」 「小説は読むけど、科学や歴史の本は一冊もないな…」
それでいいんです!それがあなたの「ホーム(得意な専門領域)」。そして、それ以外のあまり読んでいない分野が「アウェイ(未開拓領域)」です。
まずはこの「知の偏り」を自覚することが、戦略的な一歩を踏み出すための最高のスタートラインになります。
【ステップ2】目的地を決める:「なりたい自分」から逆算してみよう
現在地がわかったら、次は「どっちの方角へ冒険したいか」を考えます。これも難しく考える必要はありません。「こんなことができたらいいな」という、ぼんやりとした願いからでOKです。
ここでは、3つのアプローチをご紹介します。自分に合うものを選んでみてください。
アプローチA:課題解決型(今の悩みを解決したい!)
今、仕事やプライベートで抱えている課題を解決するヒントを、本の中から探すアプローチです。
- 課題: 「人前で話すのが苦手で、プレゼンがうまくいかない…」
- 冒険先 → 『心理学』で人の心を掴む方法を、『演劇』で表現力を、『物語創作』で魅力的な構成を学んでみる。
- 課題: 「チームのマネジメントに悩んでいる…」
- 冒険先 → 『歴史』から武将のリーダーシップを、『組織行動学』から人の動きを、『動物の生態』から強い群れの作り方を学んでみる。
直接的なビジネス書を読むより、遠回りに見えても、誰も気づかないユニークな解決策が見つかるかもしれません。
アプローチB:未来創造型(理想の自分に近づきたい!)
「3年後、5年後、こんな自分になっていたいな」という未来の理想像から、読むべきジャンルを考えるアプローチです。
- 理想像: 「データ分析に強いマーケターになりたい」
- 冒険先 → 『統計学』の入門書はもちろん、『認知科学』や『行動経済学』で人の意思決定のクセを学んでみる。
- 理想像: 「いつか新しい事業を立ち上げたい」
- 冒険先 → 『様々な業界の興亡史』で成功と失敗のパターンを、『テクノロジーの未来予測』で時代の流れを、『文化人類学』で人間の根源的なニーズを探ってみる。
未来のあなたを形作る、知識のタネを今から蒔いておきましょう。
アプローチC:好奇心探求型(ただただ、ワクワクしたい!)
「理屈はいいから、とにかく面白いことが知りたい!」という、純粋な好奇心に従うアプローチです。
- 「なぜ宇宙は始まったんだろう?」
- 「恐竜って、どんな色だったのかな?」
- 「江戸時代の庶民の暮らしって?」
一見、仕事とは全く関係ないこの「ワクワク」こそ、予想もしなかったひらめき(セレンディピティ)を連れてきてくれる最高の道しるべです。このアプローチは、雑読の醍醐味を一番味わえるかもしれません。
【ステップ3】冒険ルートを引く:具体的な「雑読プラン」に落とし込もう
さあ、いよいよ冒険マップの仕上げです。ステップ1と2で見えてきた「現在地」と「目的地」をつなぐ、具体的なルートを引きましょう。
ここで提案したいのが、「知のポートフォリオ」という考え方です。 投資で資産を分散させるように、あなたの知識もバランス良く育てていきましょう。
私のおすすめ黄金比率:「専門3:関連4:冒険3」
例えば、毎月読む本の配分をこんな風に決めてみてはいかがでしょうか。
- 専門分野(深める):30%
- 自分の軸足をブラさず、専門性を高めるための本。あなたの「ホーム」です。
- 関連分野(広げる):40%
- 専門分野の周辺領域や、ステップ2の「課題解決」「未来創造」に繋がりそうな本。アナロジー思考を鍛えます。
- 無関係な分野(冒険する):30%
- ステップ2の「好奇心探求」で気になった、全く未知の分野の本。セレンディピティの種まきです。
もちろん、この比率はあくまで一例です。「今月は新しい挑戦がしたいから『冒険』を多めにしよう」など、あなたの気分や状況に合わせて自由にカスタマイズしてくださいね。
本探しのヒント
- 芋づる式読書: 面白かった本の中で紹介されていた本や、著者が影響を受けた本を読んでみる。
- 書店で冒険: 普段は絶対に行かないコーナー(例:理工書、美術、手芸など)で、表紙やタイトルにピンときた本を直感で選ぶ「ジャケ買い」もおすすめです。
- 人に聞く: 自分とは全く違う分野で働く友人や、尊敬する上司に「人生を変えた3冊」を聞いてみる。最高の雑読リストが手に入ります。
まとめ:さあ、あなただけの冒険の旅へ出発しよう!
ここまでお疲れ様でした!これで、あなただけの「知の冒険マップ」の骨格ができたはずです。
最後に一番大切なことを。 このマップは、一度作ったら終わりではありません。
本を読んでいくうちに、あなたの興味はどんどん変化し、新たな目的地が見つかるはずです。ぜひ、定期的にこのマップを見直し、書き換え、あなただけの冒訪の記録を育てていってください。
完璧な計画なんていりません。 まずは一冊。本屋さんで、いつもと違う棚に手を伸ばしてみませんか?
その小さな一歩が、あなたの世界を広げ、未来を面白くする、壮大な冒険の始まりです。


