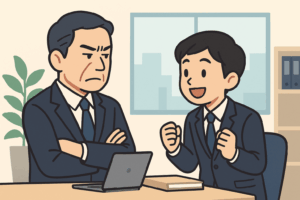「若い頃はもっとフットワークが軽かったのに…」 「新しいことを始めるのが、なんだか億劫で…」
年齢を重ねる中で、ふとそんな風に感じたことはありませんか? かつては情熱を燃やした趣味や、いつかやろうと楽しみにしていた計画が、いつの間にか「面倒くさい」という一言で片付けられてしまう。それは決してあなたが「怠け者」になったわけではありません。実は、心と身体、そして脳の自然な変化の現れなのです。
しかし、面白いことに、行動へのハードルが上がる一方で、私たちは年齢とともに「ある重要な能力」を確実に高めています。
この記事では、脳科学や心理学の知見を交えながら、なぜ行動が面倒になるのか、その一方でどんな力が伸びているのかを解き明かし、その「面倒くさい」気持ちとうまく付き合い、軽やかに行動するための具体的な方法をご紹介します。
第1章:なぜ?年を重ねると行動が「面倒」になる3つの理由
「よっこいしょ」と声に出さないと動けない。その気持ち、実は科学的な裏付けがあるのです。
1. 脳の「省エネモード」
私たちの脳は、基本的に変化を嫌い、エネルギー消費を抑えようとする「省エネ体質」です。
若い頃は、新しいことへの挑戦自体が快感でした。しかし、年齢とともに「慣れた安心できる道」を好むようになり、未知の領域に踏み出す際に脳がブレーキをかけやすくなるのです。これは、脳が危険を避け、効率的に生命を維持するための自然な仕組みともいえます。
2. 心の「ブレーキ」
たくさんの経験を積んできた、ということは、成功体験だけでなく、失敗のデータも豊富に蓄積されているということです。そのため、何かを始めようとするとき、過去の経験から無意識のうちにリスクを予測し、「やめておいた方が無難かもしれない」と慎重な判断を下しやすくなります。
これは、無鉄砲さが減り、物事を多角的に見られるようになった「賢さの副作用」とも言えるでしょう。
3. 体の「バッテリー」減少
とてもシンプルな理由ですが、体力や回復力の変化も大きく影響します。若い頃のように徹夜をしたり、無茶なスケジュールをこなしたりすることが難しくなるのは当然のこと。スマートフォンのバッテリーが経年劣化するように、私たちの身体も充電に時間がかかったり、最大容量が減ったりするのです。「動きたい気持ちはあるけれど、身体がついてこない」という感覚が、行動への意欲を削いでしまうことがあります。
第2章:でも、実はスゴイ!年齢とともに「対応力」が上がる秘密
行動するのが億劫になる一方で、私たちは素晴らしい能力を伸ばしています。それは、物事の本質を見抜き、冷静に対処する**「対応力」**です。
1. 経験が磨き上げた「結晶性知能」
心理学では、知能を大きく2つに分類します。計算や暗記のような、新しい情報をスピーディーに処理する能力を「流動性知能」といい、これは20代をピークに徐々に低下する傾向があります。
一方、経験や学習を通じて培われる知識や判断力、物事の深い理解などを「結晶性知能」 (Wikipedia)と呼びます。この知能は、なんと60歳頃まで上昇を続け、その後も高いレベルで維持されることが分かっています。
つまり、長年の経験によって様々な知識が脳内で結びつき、物事の全体像を捉え、どこが重要で、どうすれば最も効率的に解決できるかという「大局観」や「知恵」が身についているのです。若い頃のように力任せに突っ走るのではなく、状況を的確に読んで最適な一手を見つけ出す力、それが年齢を重ねた私たちの強みです。
2. 感情の波乗りが上手くなる
多くの人生経験は、感情のコントロール能力も高めてくれます。予期せぬトラブルや人間関係のいざこざに直面しても、若い頃のようにパニックに陥ったり、衝動的に行動したりすることが減ります。「まあ、こういうこともあるだろう」と冷静に受け止め、感情の波に乗りこなす術を、私たちは自然と身につけているのです。
「面倒くさい」と感じるのは、物事を始める前に多角的に検討し、リスクを分析できるようになった、脳が次のステージに進化した証拠とも言えるのかもしれません。
第3章:「面倒くさい」を「やってみよう!」に変える5つのスイッチ
では、その成熟した脳と心、そして身体とどう付き合い、気持ちよく行動に移していけばよいのでしょうか。今日から試せる5つのスイッチをご紹介します。
スイッチ1:ベイビーステップで始める
「やるぞ!」と意気込むから、行動のハードルが上がります。目標を極限まで小さく分解してみましょう。
- 例:「ウォーキングを始める」 → 「とりあえずウェアに着替えるだけ」
- 例:「部屋を片付ける」 → 「テーブルの上からDMを1枚捨てるだけ」
- 例:「読書をする」 → 「本を開いて1行だけ読む」
心理学では、何かを始めると脳の「側坐核(そくざかく)」という部分が刺激され、やる気が出てくると言われています。最初の0.1歩を踏み出すことさえできれば、脳が勝手に次のステップへと後押ししてくれます「5分だけ」を合言葉にしてみましょう。
スイッチ2:「未来の自分」からご褒美をもらう
行動した後に得られるポジティブな感情やメリットを、具体的に想像してみましょう。
- 「この書類を片付けたら、スッキリした気分で美味しいコーヒーが飲めるぞ」
- 「運動したら、今夜はぐっすり眠れて、明日の朝は気持ちよく起きられるだろうな」
行動そのものではなく、行動によって得られる「ご褒美」に意識を向けることで、脳は「それを手に入れるために行動しよう」と判断しやすくなります。
スイッチ3:「ついで」と「ながら」で動く
新しい習慣をゼロから作るのは大変です。既存の習慣に、新しい行動をくっつけてみましょう。
- 歯磨きをしながら、ついでにスクワットを10回やる。
- お湯を沸かしながら、ながらでキッチンのシンクを磨く。
- 通勤電車の中で、ついでに資格試験の単語を5つ覚える。
「ついで」や「ながら」は、意志の力に頼らず、行動を自動化する賢い方法です。
スイッチ4:感情を実況中継してみる
「あ、今、面倒くさいって感じてるな」「やるべきことから逃げたいと思ってるな、自分」というように、自分の感情を客観的に観察(メタ認知)してみましょう。
感情に飲み込まれるのではなく、一歩引いて眺めてみることで、「面倒だと感じていること」と「実際に行動すること」は別問題だと切り離せるようになります。感情は天気のようなもの。ただそこにあるだけで、それに振り回される必要はないのです。
スイッチ5:あえて「非効率」を楽しむ
年齢を重ねると、効率や生産性を重視しがちです。しかし、時にはその考えを手放し、プロセスそのものを楽しむ視点を持ってみましょう。
例えば、庭の手入れを「雑草を取る作業」と捉えるのではなく、「土の匂いや風を感じる時間」と捉えてみる。料理を「食事の準備」ではなく、「新しいレシピに挑戦する実験」と捉えてみる。
「やらされ感」が「やりたい感」に変わった時、面倒くさいという気持ちは自然と消えていきます。
まとめ
年齢を重ねることで訪れる心や身体の変化は、決してネガティブなことばかりではありません。行動への腰が重くなるのは、物事を深く考えられるようになった賢さの裏返しであり、その一方で、物事の本質を見抜く「対応力」という素晴らしい武器を私たちは手にしています。
「面倒くさい」という気持ちは、あなたを責めるサインではなく、「どうすればもっと楽に、楽しくできるかな?」と工夫を生み出すための大切なきっかけです。
ぜひ、今日ご紹介した5つのスイッチの中から、どれか一つでも試してみてください。昨日より少しだけ軽やかに動ける自分に出会えるはずです。あなたの毎日が、より豊かで快適なものになることを心から応援しています。