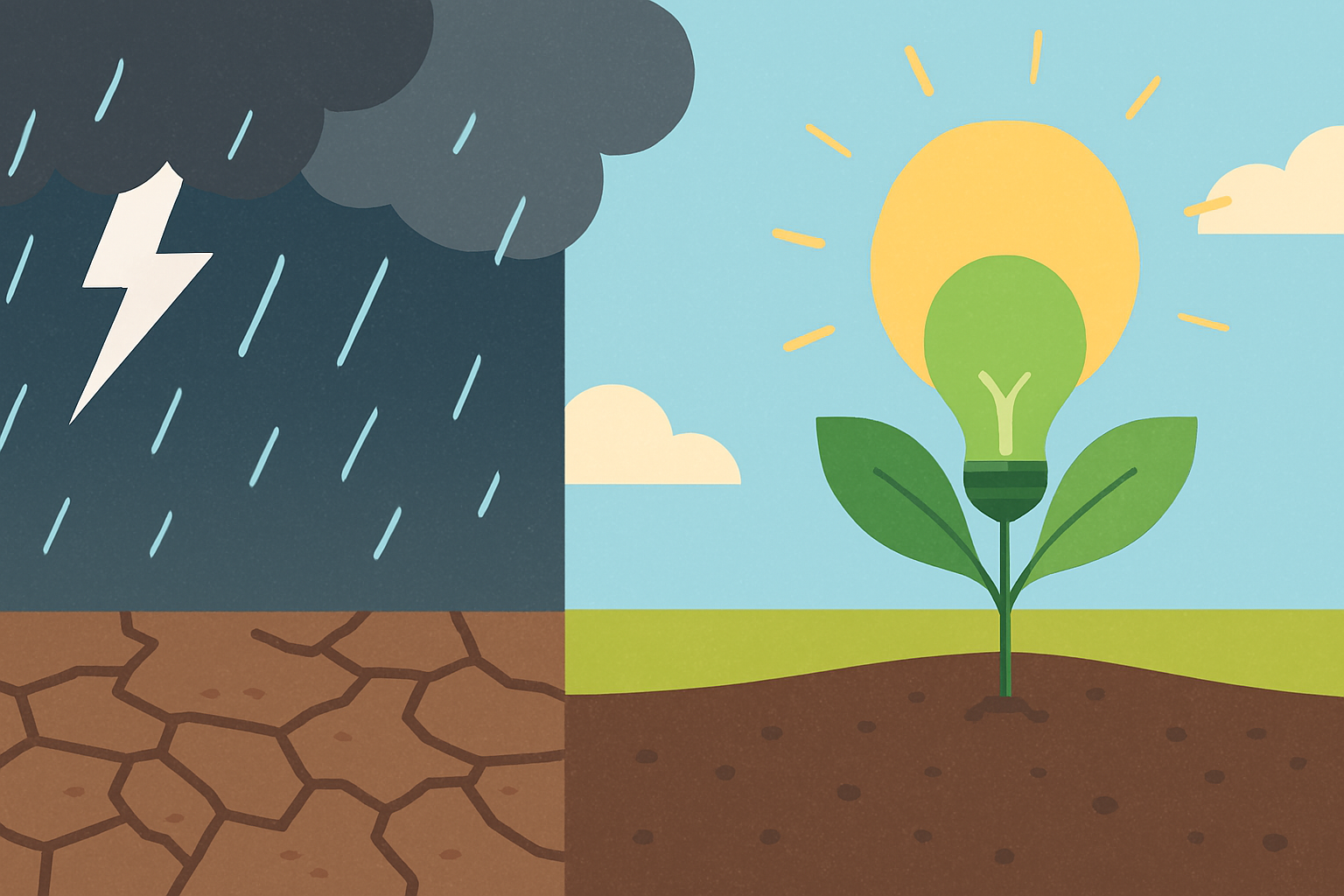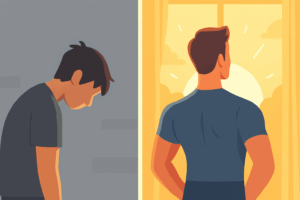「もっと厳しく言わなきゃダメなのかな…」
「でも、相手を追い詰めるようなことはしたくない…」
部下や後輩、あるいは我が子に対して、そんな風に悩んだことはありませんか?
リーダーや親御さんに共通する悩みとして「どうすれば相手をやる気にさせ、成果に導けるのか」というものがあります。
昔ながらの「見て覚えろ!」「気合が足りない!」といった厳しいスタイルは、短期的に人を動かすことはあっても、長い目で見るとうまくいかないケースがほとんどです。むしろ、相手の心を閉ざさせ、パフォーマンスを低下させてしまうことも少なくありません。
今日の記事では、「なぜ、厳しい人より安らぎを与える人の方が、結果的に人を成長させ、成果に導けるのか」を、心理学の視点から紐解き、明日から実践できる具体的なアクションプランをご紹介します。
これを読めば、あなたも「あの人がいると、なぜか頑張れる」と自然に思われる、素敵なリーダーに近づけるはずです。
なぜ「ただ厳しいだけ」ではダメなのか?脳は“恐怖”でフリーズする
まず、大前提として知っておいてほしいことがあります。それは、人間の脳は、恐怖や強いストレスを感じると、創造性や思考力が著しく低下するということです。
心理学ではこれを「扁桃体ハイジャック」と呼んだりします。
厳しい言葉で叱責されたり、常に監視されているようなプレッシャーを感じたりすると、脳の「扁桃体」という部分が「危険だ!」と判断し、生存本能がオンになります。すると、論理的に考えたり、新しいアイデアを生み出したりする「前頭前野」の働きが抑制されてしまうのです。
これでは、まるでアクセルとブレーキを同時に踏んでいるようなもの。本人がいくら「頑張ろう!」と思っても、脳が最高のパフォーマンスを発揮できる状態ではありません。
つまり、表面的な厳しさは、相手から「考える力」や「挑戦する意欲」を奪ってしまう危険性があるのです。
「安らぎ」が成果を生む3つの理由
では、なぜ「安らぎを与える人」のもとで、人は成長し、成果を出すのでしょうか?それには、ちゃんとした理由があります。
1. 心理的安全性が「挑戦」の土台を作る
最近よく聞く「心理的安全性」という言葉。これは、「このチームの中では、何を言っても大丈夫」「失敗しても非難されることはない」と、メンバーが心から感じられる状態のことです。
Google社が大規模な調査の結果、「生産性の高いチームの最も重要な共通点」として発見したことで有名になりました。
考えてみてください。あなたが何か新しいアイデアを試そうとするとき、「失敗したらどうしよう…」「変なこと言ったら笑われるかも…」という不安があったら、一歩を踏み出せますか?
安らぎを与えるリーダーは、まさにこの「心理的安全性」を作り出すプロです。
- 失敗を責めるのではなく、「いい挑戦だったね!何が学べた?」と一緒に振り返る。
- どんな小さな意見でも、「なるほど、そういう考え方もあるね!」と一度受け止める。
こうした関わりが、「ここなら安心して挑戦できる」という信頼感を生み、メンバーの主体的な行動を引き出すのです。
2. ポジティブな感情が「視野」を広げる(拡張形成理論)
心理学者のバーバラ・フレドリクソン(Wikipedia) が提唱した「拡張形成理論」(broaden-and-build theory, Wikipedia) をご存知でしょうか?
これは、喜び、感謝、希望といったポジティブな感情を抱いているとき、人の思考や行動の選択肢は広がる(拡張する)という理論です。
例えば、上司から「君のレポート、すごく分かりやすかったよ。ありがとう!」と感謝されたら、どんな気持ちになりますか?
「嬉しいな!」「次も頑張ろう!」「もっと良いものを作るにはどうすればいいかな?」と、自然と前向きなアイデアが浮かんできませんか?
これがまさに「拡張」の状態です。
安らぎを与える人は、相手の良いところを見つけて認めたり、感謝を伝えたりすることで、相手の心にポジティブな感情を灯します。その結果、相手はより広い視野で物事を考え、創造的な解決策を見つけられるようになるのです。
3. 「内発的動機づけ」に火をつける
人に動いてもらうための動機づけには、「アメとムチ(報酬や罰)」で動かす「外発的動機づけ」と、本人の「やりたい!」「面白い!」という気持ちから生まれる「内発的動機づけ」があります。
長期的に高いパフォーマンスを発揮するのは、どちらだと思いますか?
答えは、圧倒的に後者の「内発的動機づけ」です。
厳しいだけの関わりは、相手を「怒られたくないからやる」という外発的動機づけに頼りがちです。これでは、指示されたことしかやらない「指示待ち人間」を生んでしまいます。
一方、安らぎを与える人は、相手との対話を通じて、その人が何に興味があり、何を大切にしているのかを理解しようとします。そして、仕事や課題を、その人の興味・関心と結びつけてあげるのです。
- 「〇〇さんは、人をサポートするのが得意だから、この新人の教育係をお願いできないかな?」
- 「データ分析が好きだって言ってたよね。この部分、ちょっと君の視点で分析してみてくれない?」
このように、本人の「やりたい」という気持ちに火をつけることで、人は自ら考え、工夫し、期待以上の成果を出してくれるようになります。
明日からできる!「安らぎ系リーダー」になるための3ステップ
では、具体的にどうすればいいのでしょうか?難しく考える必要はありません。まずは小さなことから始めてみましょう。
- Step1:聞く姿勢を「前のめり」にする
相手が話しているとき、スマホを見たり、PC作業をしたりしていませんか?まずは、体を相手の方に向け、少し前のめりになるくらいの姿勢で、「うん、うん」「それで?」と相槌を打ちながら聞いてみてください。「あなたの話を真剣に聞いていますよ」というメッセージが、相手に絶大な安心感を与えます。 - Step2:「結果」だけでなく「プロセス」を承認する
たとえ結果が伴わなくても、「あの難しい案件に、粘り強く取り組んでくれたね」「準備にすごく時間をかけてくれたのが伝わってきたよ」など、相手の努力や工夫した点(プロセス)を具体的に言葉にして伝えてみましょう。承認欲求が満たされ、「ちゃんと見てくれている」という信頼関係が深まります。 - Step3:「教えて」と頼ってみる
「この件、〇〇さんの方が詳しいと思うんだけど、ちょっと教えてくれない?」と、あえて相手に頼ってみるのも効果的です。人は誰かに頼られると、「自分は必要とされている」と感じ、自己肯定感が高まります。これは「人に教える」という行為が、最も学びが深いこと(学習の定着率)とも関係しています。
まとめ:厳しさは「最後のスパイス」。基本は安心できる「土壌」づくり
誤解しないでほしいのは、「厳しさ」が完全に不要だというわけではないということです。ときには、相手の成長のために、ビシッと指摘しなければならない場面もあります。
しかし、それはあくまで「信頼関係」という土台があってこそ響くもの。
普段から安心できる土壌を丁寧に耕しておけば、たまに加える厳しさというスパイスは、相手の成長を促す最高の栄養になるのです。
まずは、相手の心を「安全基地」のように温かく包み込むことから始めてみませんか?
きっと、あなたの周りには、安心してのびのびと能力を発揮する人たちが増え、チーム全体がポジティブなエネルギーで満たされていくはずです。
この記事が、あなたの明日からのコミュニケーションのヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。