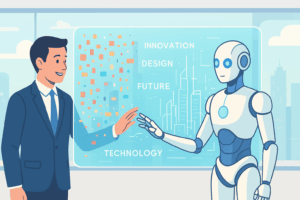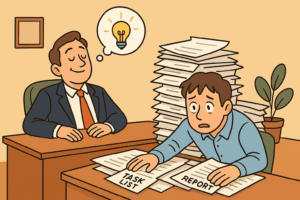システムの安定稼働を考えるとき、必ず登場するキーワード「冗長性」。でも、この言葉、少し難しく聞こえませんか?
「冗長性を高めましょう!」と言われても、
「え、それってサーバーを2台にすればいいの?」
「コストがかかりすぎるんじゃない?」
「そもそも、うちのサービスにどこまで必要なの?」
なんて、疑問が次々と湧いてくる方も多いはず。
この記事では、そんな「冗長性」のモヤモヤを解消します。システムの専門家だけでなく、ビジネスの意思決定に関わるすべての方に「なるほど!」と思っていただけるよう、冗長性の適切な量の決め方から費用の考え方まで、わかりやすく解説していきます。
そもそも「冗長性」って、なんのため?
一言でいうと、冗長性は「もしもの時のための保険」です。
パソコンで大事なファイルを作成するとき、バックアップを取りますよね?あれも立派な冗長性です。1つのファイルが壊れても、もう1つあれば安心。システムにおける冗長性も、考え方は同じです。サーバー、ネットワーク機器、電源などが1つ故障しても、予備があるおかげでサービスを止めずに継続できる。これが冗長性の最大の目的です。
サービスが停止すると、売上の機会損失だけでなく、お客様からの信頼も失ってしまいます。その損害を未然に防ぐための、いわば「転ばぬ先の杖」なのです。
「適切な量」はどう決める?魔法の数字はありません
「じゃあ、冗長性は高ければ高いほどいいんだ!」と思ってしまいがちですが、それは早計です。なぜなら、冗長性を高めるにはコストがかかるから。なんでもかんでも二重化、三重化していたら、あっという間に予算が尽きてしまいます。
では、どうやって「適切な量」を決めればよいのでしょうか?
ポイントは、「守りたいものは何か?」を明確にすることです。そのために、2つの重要な指標(モノサシ)を使いましょう。
モノサシ①:RTO(目標復旧時間)
RTO(Recovery Time Objective)は、「システムが停止してから、どれくらいの時間で復旧させたいか」という目標時間です。
- RTOが短い(例:数秒~数分)
- ECサイトの決済システムや、工場の生産管理システムなど、停止が許されないシステム。
- 瞬時に切り替わる仕組み(HAクラスタなど)が必要で、高い冗長性が求められます。
- RTOが長い(例:数時間~1日)
- 社内の情報共有ツールや、開発環境など、多少の停止が許容できるシステム。
- バックアップからの復旧で間に合う場合もあり、冗長性のレベルを抑えることができます。
「このシステムが止まったら、何分でお客様や業務に影響が出るだろう?」と考えてみてください。それがRTOを決めるヒントになります。
モノサシ②:RPO(目標復旧時点)
RPO(Recovery Point Objective)は、「障害が発生した際に、どの時点のデータまでなら失われても許容できるか」という目標です。
- RPOが短い(例:0秒)
- 銀行の勘定系システムや、オンラインゲームの課金データなど、1秒たりともデータの損失が許されないシステム。
- 常にデータをリアルタイムで同期する必要があり、非常に高いコストがかかります。
- RPOが長い(例:24時間)
- ブログサイトや、定期的に更新される分析データなど。
- 1日1回のバックアップで十分な場合が多く、コストを抑えられます。
「最悪、昨日の状態に戻っても大丈夫か?それとも1分前のデータが必要か?」を考えるのがRPOです。
このRTOとRPOをビジネスの視点で定義することが、適切な冗長性を決めるための最も重要な第一歩です。技術的な話の前に、まずこれを決めましょう。
費用の考え方:「コスト」 vs 「リスク」の天秤
冗長性の費用を考えるとき、単純な機材の購入費やクラウドの月額料金だけを見てはいけません。ここで考えるべきは「投資対効果」です。
冗長性のコストの内訳
- 導入コスト(イニシャルコスト): サーバー、ストレージ、ネットワーク機器などの購入費用、ソフトウェアのライセンス費用、設計・構築費用など。
- 運用コスト(ランニングコスト): データセンターの利用料、クラウドサービスの月額料金、保守・メンテナンス費用、監視のための人件費など。
これらは、いわば「保険料」です。
比較すべきは「停止した場合の損失額」
この「保険料」が高いか安いかを判断するためには、「もしも」が起きたときの損失額を試算する必要があります。
- 機会損失: サービス停止中の売上減、新規顧客獲得の機会ロスなど。
- 信用の失墜: 顧客離れ、ブランドイメージの低下、SNSでの炎上など。(金額換算は難しいですが、最も大きなダメージになり得ます)
- 復旧作業コスト: エンジニアの人件費、外部への依頼費用など。
これらの損失額(リスク)と、冗長性にかけるコストを天秤にかけるのです。
(冗長性コスト) < (停止した場合の想定損失額)
この不等式が成り立つ範囲で、最適な冗長性のレベルを決定するのが、賢い投資判断と言えるでしょう。
例えば、1時間の停止で100万円の損失が出るECサイトなら、年間数十万円の冗長化コストは「安い保険」かもしれません。しかし、停止しても社内業務が少し滞る程度のシステムに、同じコストをかけるのは「過剰な保険」になってしまいます。
まとめ:あなたのビジネスに合った「ちょうどいい」を見つけよう
冗長性は、闇雲に導入するものではありません。
- 守りたいものを明確にする:あなたのビジネスにとって、どのシステムが「心臓部」ですか?
- RTO/RPOを決める:「何分で復旧?」「どの時点のデータが必要?」をビジネス視点で定義しましょう。
- コストとリスクを天秤にかける:「保険料」として支払うコストと、事故が起きたときの損失額を比較検討しましょう。
この3つのステップを踏むことで、技術者も経営者も納得できる、あなたのビジネスにとって「ちょうどいい」冗長性のレベルが見つかるはずです。
「とりあえずサーバーを2台に…」と考える前に、一度立ち止まって、ビジネスの視点から「もしもの時」を具体的に想像してみてください。それが、賢く、そして力強いシステムを作るための最短ルートなのです。