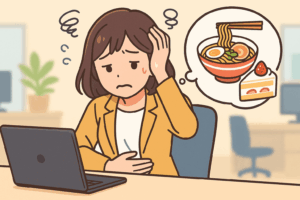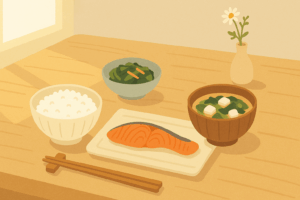「舌切り雀をいじめる、あのおばあさん…どうしていつも“おばあさん”なんだろう?」
子どもの頃、誰もが一度は抱いたかもしれない、この素朴な疑問。
今日は、この問いを入り口に、あなたを知的な冒険の旅へとお連れします。
この旅は三つの章で構成されています。
第一章では、物語の「表層」を探る社会学や民俗学の岸辺を歩き、
第二章では、歴史や神話が眠る「深層」の海へ潜り、
そして第三章では、あなた自身の心の「最深部」へと挑みます。
読み終える頃、あなたが見る物語の世界は、きっと色鮮やかに、そして少しだけスリリングに変わっているはずです。さあ、冒険の準備はいいですか?
第一章:【岸辺の散策】物語の「なぜ?」を解き明かす3つのヒント
まずは、私たちの身近な世界からヒントを探してみましょう。なぜ「いじわるばあさん」は、物語の悪役としてこんなにも“しっくり”くるのでしょうか?
ヒント①:家庭内の「小さな権力者」だったから(社会学の視点)
昔の社会、特に農村では、家の外の仕事や村の決定権は男性(おじいさん)が握っていました。一方、家の中のことは、すべて女性(おばあさん)が取り仕切っていました。
お金の管理、日々の食事、そしてお嫁さんへの指示…。おばあさんは、いわば家庭内という「小さな王国」の女王様だったのです。
現実の世界でも「嫁姑問題」が起こりやすいように、この閉ざされた空間での権力は、時に「いじわる」や「欲」として現れやすくなります。物語は、そんな現実社会のリアルな人間関係を映し出す鏡。だから、家の「中」で起こるトラブルの象徴として、「いじわるなおばあさん」が登場しやすかったのです。
ヒント②:この世とあの世の「境界に立つ人」だったから(民俗学の視点)
民俗学の世界では、老婆は「この世とあの世の境界に立つ、ミステリアスな存在」と考えられていました。
赤ちゃんを取り上げる「産婆」さんや、亡くなった人を弔う役目を担っていたのは、主に経験豊かな年配の女性でした。彼女たちは「生」と「死」という、人間にとって最も神秘的な瞬間に立ち会う存在だったのです。
このことから、老婆は人知を超えた不思議な力を持つと信じられました。西洋の「魔女」や日本の「山姥(やまんば)」が老婆の姿で描かれるのも同じ理由です。その力は、良い方向に働けば「知恵」になりますが、悪い方向に働けば「呪い」や「いじわる」になる…。そんな少し怖いイメージが、「いじわるばあさん」のキャラクター像に繋がっていきました。
ヒント③:物語を最高に面白くする「装置」だったから(物語構造の視点)
物語を面白くするには、魅力的な「敵」が不可欠です。
若く美しい主人公の対極に、「老い」と「醜さ(心の)」を象徴する老婆を置くことで、主人公の輝きは一層増します。光と影の効果ですね。
さらに、「おばあさん=優しい」という私たちの固定観念を裏切るからこそ、その「いじわる」は強烈なインパクトを残します。物語は、この裏切りを利用して、私たち読者の感情を揺さぶり、物語にグッと引き込んでいたのです。
第二章:【深海へのダイブ】歴史と神話に眠る「太母」の記憶
さて、岸辺の散策はここまで。ここからは、日本の歴史と神話が眠る、もっと深い海へと潜っていきましょう。
深層①:聖母か、怪物か。神話に刻まれた「二つの顔」
日本の神話には、この世界の成り立ちに関わる、偉大な母神が登場します。国生みの母「イザナミ」です。彼女は多くの神々を生み出す「聖なる母」でしたが、火の神を産んだことで死んでしまい、黄泉の国(死者の国)の恐ろしい存在へと変貌してしまいます。
「生命を生み出す聖なる母」と「死と穢れを司る恐ろしい存在」。
この「太母(グレートマザー)」が持つ二つの顔の記憶は、日本の物語のDNAに深く刻み込まれました。そして、
- 「優しいおばあさん」として、聖なる母の側面が…
- 「いじわるばあさん」として、恐ろしい母の側面が…
それぞれ物語の中で役割を担うようになったのです。彼女たちのルーツは、神話の時代にまで遡る、壮大なものだったのですね。
深層②:なぜ彼女は「悪役」を演じるしかなかったのか
物語を一つの「システム」として見てみましょう。
物語という機械は、「善vs悪」「若さvs老い」といった対立するエネルギーで動きます。
もし、『舌切り雀』のおばあさんが雀の舌を切らなかったら?物語は始まりません。
「いじわるばあさん」の役割は、この停滞した世界に事件を起こし、物語のエンジンを始動させる「スイッチ」を押すことだったのです。
つまり、彼女は悪人だったから意地悪をした、というより、物語が始まるために、誰かが「悪役」という名のスイッチを押す必要があった。そして、その役に最もふさわしい存在として、歴史や神話のイメージを背負った「老婆」が選ばれたのです。彼女は、物語を動かすためだけに用意され、最後には役目を終えて退場する、悲しいほどに機能的な存在だったのかもしれません。
第三章:【最深部への挑戦】鏡の中に映る「私たちの未来」
いよいよ最後の旅です。最も深く、そして最も私たちの心に突き刺さる領域へ。この問いの矛先は、物語を飛び出し、「私たち自身」に向けられます。
真相①:「いじわるばあさん」は、未来の私たちだった?
「いじわるばあさんが罰せられて、めでたしめでたし」。
この結末に、私たちはなぜホッとするのでしょうか?
哲学的に見ると、それは「自分とは違う存在」を排除することで安心したい、という人間の根源的な心理が働いているからかもしれません。
老い、孤独、貧しさ、社会からの孤立…。
「いじわるばあさん」は、私たちが目を背けたいあらゆる「負」の要素を一身に背負わされた存在です。私たちは彼女を「欲張りだから」と単純化し、断罪することで、自分たちが抱える「老いへの恐怖」や「孤独への不安」から目をそらしているだけではないでしょうか。
そう考えると、彼女は「悪役」などではない。
彼女は、社会の隅で声を上げられずにいる人々や、いつか老いて孤独になるかもしれない「未来の私たち自身」を映し出す“鏡”なのです。
私たちが物語の中で彼女を指差し、「悪だ」と笑うとき、私たちは鏡に映った自分の未来の姿から、無意識に目を背けているのかもしれません。
旅の終わりに:物語が私たちに問いかけること
「いじわるばあさん」を巡る、三つの章からなる冒険の旅、いかがでしたか?
彼女は、単なる昔話の登場人物ではありませんでした。
社会のリアルな姿を映し、神話の記憶を背負い、そして私たちの心の奥底に眠る恐怖や不安までも引き受けてくれる、あまりにも深く、挑戦的な存在だったのです。
次にあなたが物語の中で彼女に出会ったなら、ぜひ思い出してください。
その意地悪な顔の裏には、何千年もの歴史と、人間社会の複雑なドラマが隠されていることを。そして、その物語を読んでいる「あなた自身」の心も、静かに映し出されていることを。
「いじわるばあさん」は、私たちに問いかけ続けています。
「あなたは、自分とは違う存在を、理解しようとしていますか?」と。
物語の世界は、私たちが思っている以上に、ずっと深く、私たちの現実と繋がっているのです。